子どもの遊び食べで見られる行動は?食べ物で遊ぶ理由や対処法も紹介
育児
2022.01.04
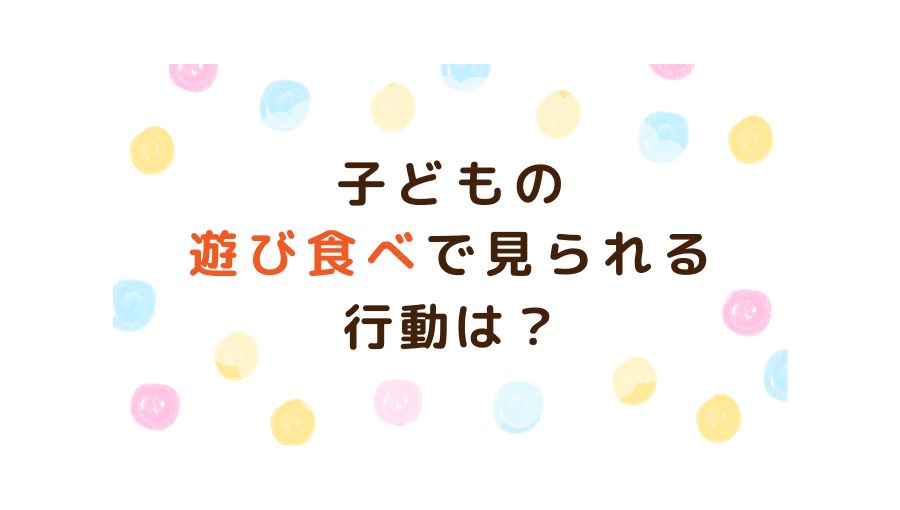
目次
目次
「せっかく作ったご飯でどうして遊んでしまうの?」
「遊び食べはしつけがちゃんとできていないから?」
「どうしたら遊び食べをやめて、ちゃんとご飯を食べてくれるんだろう」
ある時期になると子どもは、ご飯の時に食べもので遊ぶいわゆる遊び食べを始めます。保護者としては、ちゃんとご飯を食べて欲しい気持ちが強くなりますが、それに反して遊び食べはどんどんエスカレートしていくでしょう。
この記事では、なぜ子どもは遊び食べをするのか、遊び食べにどう対処していけばよいかなど、遊び食べについて紹介します。
遊び食べにも理由があることを知ると、子どもの遊び食べもイライラせずにしっかりと受け止めることができるでしょう。また、少しでも対応が楽になるなど対処法があることもわかります。
子どもの遊び食べに悩んでいる保護者の方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
子どもの遊び食べで見られる行動

離乳食をはじめてしばらく経つと、子どもは遊び食べという行動をとったりします。
その例として、食べものを手やスプーンでぐちゃぐちゃと混ぜる、食べものを床に落とす、スプーンで皿を叩く、飲みものの中に食べものを入れる、食事中に席を立って動き回る、テーブルの上に乗ったりする、などです。
子どもが遊び食べをする4つの理由

大人から見ると、遊び食べは行儀が悪いとされる行動です。そのため、必死にやめさせようとしたり、自分の育て方が良くないのではなどと考えたりしがちです。
しかし、子どもが遊び食べをするのには理由があります。その理由を見ていきましょう。
- ・食べ方を触って確かめている
- ・お腹が空いていないため遊び食べする
- ・周りの大人に注目してほしくて遊び食べする
- ・好奇心で探索行動をする成長の一環
1:食べ方を触って確かめている
子ども達は五感を回転させて、全身でさまざまなことを学びながら成長していきます。大人のように、目で見て頭で考え、理解し判断するという発達段階ではありません。
この食べ物は触ったら熱い、やわらかい感触であるということを、実際に体験して学びます。実際に触ることで、この食べ物はどういうものなのかという理解を進めている段階です。
2:お腹が空いていないため遊び食べする
大人はお腹がいっぱいになれば、食事を終えます。子どもは、お腹がいっぱいになっても食事を自分で終えることはできません。保護者が気付かなければ、目の前には食べものが置かれている状態です。
また、食事の時間だからと食事を用意しても、お腹が空いていなければ子どもは食べようとはしません。
そのような時に、子どもはよく遊び食べをします。食事で十分にお腹が満たされたか、お腹自体がすいていないのか保護者はよく見極めましょう。
3:周りの大人に注目してほしくて遊び食べする
子どもが遊び食べを始めると、周りの大人が大慌てしたり驚いたりすることがあります。
この大人の反応が、子どもにとって自分が注目されていると思わせてしまい、自分に注目してもらいたくてわざと遊び食べをする子どももいます。
4:好奇心で探索行動をする成長の一環
遊び食べは、大人の価値観でいうと食事の時に適さないふるまいであり、正すものであることになります。
しかし、子どもにしてみれば、食器をスプーンで叩いたらどのような音が出るのだろう、ご飯を手で触ったらどのような感じがするのだろう、といった好奇心が生んだ行動といえるでしょう。
このように遊び食べは子どもにとって、好奇心にもとづく探索行動の一種であるため、順調に成長している証であるといえるでしょう。
遊び食べのおすすめの対処法
関連記事一覧
-
叱ると怒るの違い ポイント5つ 親が子供を叱ると怒るの違いは重要な親子コミュニケーションの一部で、以下のようにいくつかの主要なポイントで区別することができます。目的叱ることは主に教育的な目的があります。子供の間違った行動を正し、正しい行動を学ばせること...
育児
2023.07.31
-
今が旬!「きのこ」を味わおう 準備も簡単!きのこの食育きのこは手で簡単にほぐすことができるので、1歳のお子さんから「食材に触る」体験ができます。一般的なきのこは通年手に入るものなので、単独で使っても秋らしさを感じることは難しいかもしれませんが、いろい...
育児
2022.10.13
-
懐かしの給食の味をご家庭で!「きな粉揚げパン」 揚げパンの始まり揚げパンは昭和27年、東京の大田区の小学校で生まれました。風邪で学校を休んだ生徒に栄養をつけてもらおうと、残ったパンで作ったことがきっかけといわれています。現在では衛生的な側面から休んだ生徒に給食を届ける...
育児
2022.10.13
-
子供への愛情表現が苦手のままだとどうなる?愛情不足が及ぼす影響や克服法を解説 「子供への愛情が不足していると将来どうなる?」「愛情表現が苦手で子供に愛情が伝わっているか不安」「苦手な愛情表現を克服する方法が知りたい」子供の愛情不足が将来にどのような影響を及ぼすのか知りたいひともいるのではないでしょ...
育児
2022.09.29
-
母親が娘を苦手なのは普通?関係性が悪くなった理由やアドバイスも解説 「娘と接するのがなぜこんなにムカつくの?」「娘の態度や言い方が苦手で不安になってきた」「娘と関係をよくしたいけれど、対応するのが辛い」このように、可愛いはずの子供が成長するにつれて、苦手に感じるようになる母親は少なくあり...
育児
2022.09.29
