高校生の不登校を克服させるには?きっかけや保護者ができること
教育(高校生)
2021.07.09
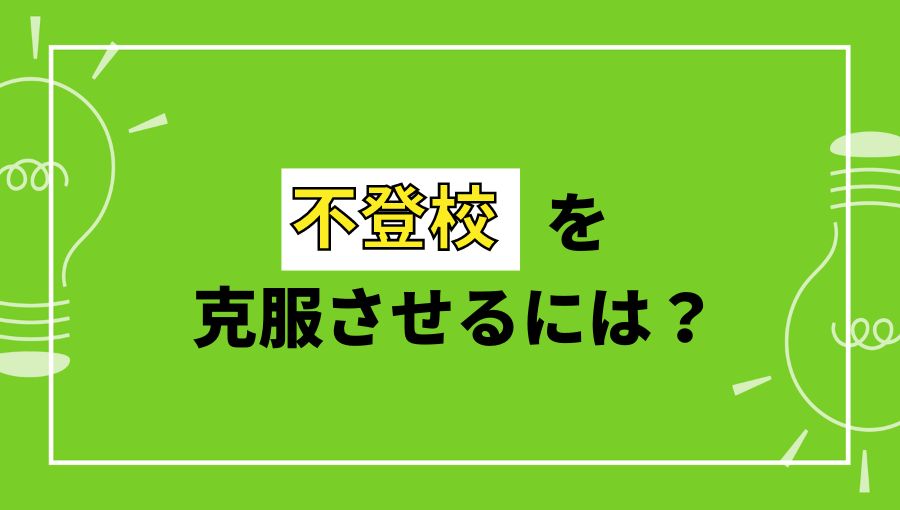
目次
目次
高校生の不登校生徒数はどれくらい?
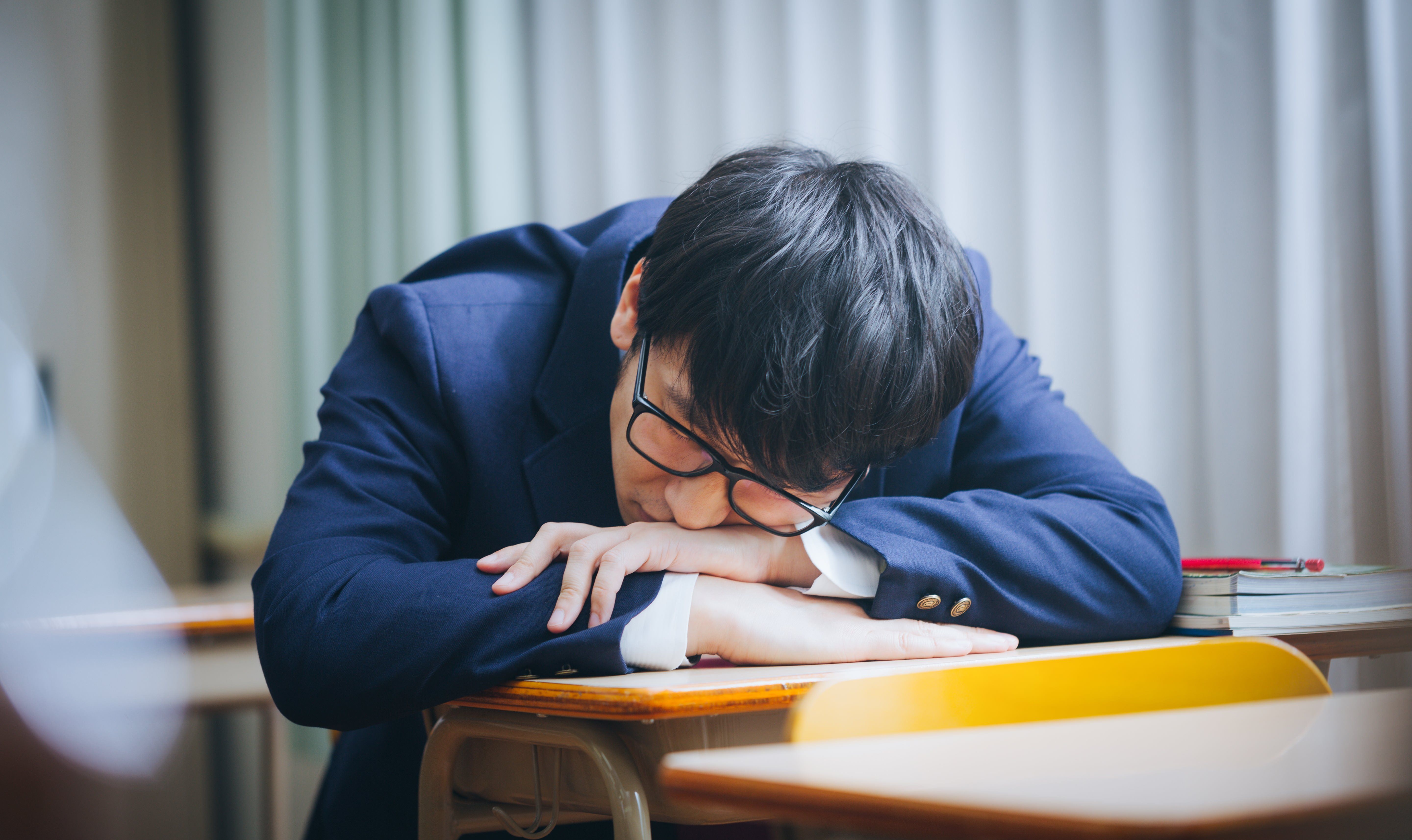
文部科学省の調査によると、令和元年の不登校の高校生は50,100人となっています。平成16年では67,500人だったので、不登校の高校生数は減少しています。
ただし、近年ではその数がほぼ横ばい状態となっています。また、小・中学校の不登校生の数を合わせた全体の数であれば、年々その数は大きな増加傾向にあります。
そのため、不登校の問題は他人事ではなく、自分の子供に起こる可能性がある問題として保護者は把握しておく必要があります。
出典:高等学校における不登校の状況について|文部科学省
参照:https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20201204-mxt_syoto02-000011235_2-1.pdf
不登校が最も多い時期とは
不登校になってしまいやすい時期は夏休みや冬休みなどの長期の休みが明けるタイミングと言われています。
子供が不登校になる原因はいろいろとありますが、長い休みのうちに自分が学校で抱えている問題について考えてしまい、ストレスを感じてしまうことが原因の1つと考えられています。
学校でのストレスを自覚してしまうことで、休み明けに登校することが精神的な負担と感じてしまい、子供は学校に行きたくないと感じるようになってしまいます。
中学生の不登校との違い
中学校は義務教育ですが、高校は義務教育ではありません。そのため、高校生が不登校となった場合には、学校を辞めるという選択もできます。しかし、中学生の場合は義務教育なので、学校を辞めることはできず、簡単に転校するという選択もできません。
この違いがあることで、不登校となった中学生と高校生では保護者の対応方法が変わることになるでしょう。
高校生が不登校になってしまう理由3選

保護者が不登校となった子供に対応する際には、不登校となった理由に合わせた方法で対応をする必要があります。
高校生が不登校となる理由はいろいろありますが、その中でも起こりやすい理由がいくつかあるので、その理由にはどのようなものがあるのか把握しておきましょう。
1:学校生活で溜まったストレス
子供は学校生活の中でいろいろなストレスを抱えます。そのストレスを休日に回復できないと、どんどん蓄積されてしまって許容量を超えてしまい、休み明けに学校へ行けなくなってしまいます。
特に、長期の休みは学校で抱えるストレスについて考えてしまう、ストレスに耐えてきたが我慢への集中力が途切れるなど、不登校になるきっかけとなってしまう場合があります。
2:学校というものへのモチベーション低下
夏休みや冬休みなどの長い休みに入ると、学業から離れてしまうことになります。そのため、休みの間に子供の学校に対するモチベーションが低下してしまう場合があります。
また、長い休みのうちに子供の生活リズムが乱れてしまっている場合は、学校がある際の生活リズムに戻さなければいけません。しかし、学校へのモチベーションが低下していることで、学校に行く生活リズムに戻すことができず、学校に行けなくなってしまう場合があります。
3:進路選択のミス
高校に進学する際には、子供はいろいろな理想を持ってその進学先を選びます。しかし、高校に進学後、思っていたような学校生活が送れないということはよくあります。
学校生活の理想と現実の差にストレスを感じるようになると、学校へのモチベーションが下がってしまい、不登校の原因となってしまう場合があります。
高校生の不登校克服のきっかけ6選

不登校になった高校生の子供に、また学校に行ってもらいたいと考える保護者もいます。そのため、不登校となった高校生はどのようなことがきっかけがあれば、不登校を克服できるのか知っておきましょう。
また、不登校は他人事ではないので、子供が不登校でなくても、予備知識として知っておくようにしましょう。
1:朝きちんと起きられた
関連記事一覧
-
国語がすべての勉強の基礎になるポイント4つ 国語は、コミュニケーションの基礎となる 国語は私たちが日常的に使うコミュニケーション手段です。言葉を使って情報を伝えたり、他人と意見を交換したりするためには、適切な文法や語彙を持つ必要があります。国語の基礎を学ぶこと...
教育(中学生)教育(高校生)教育(小学生)
2023.07.25
-
現代文が苦手な原因って?克服するポイントやおすすめの参考書を解説 「現代文の勉強の仕方が分からない」「記述式問題の解き方が分からない」「記述式問題は得意だけどマーク式問題はどうも苦手だなあ」などと悩んでいるお子さんをお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。 この記事は、...
教育(高校生)
2022.09.29
-
ベクトルが苦手な理由とは?克服するコツや高校生におすすめの参考書を詳しく解説 「ベクトルって何だっけ?」「ベクトルが苦手すぎる...」 このような方はいらっしゃいませんか。ベクトルは他の数学の分野と比べて独自の方法や考え方を要求している分野です。そのため、慣れない方には苦手意識をお持ちの...
教育(高校生)
2022.09.29
-
高校3年生が苦手な理科を克服するための勉強法とは?夏休みの過ごし方も解説 「理科科目の効率的な勉強法って?」「苦手な理科の得点を夏休みのうちに上げたい」「高校3年生の夏休みはどう過ごせばいいの?」上記のように理科の勉強法が分からなかったり夏休みをどのように過ごしたらいいのか分からない受験生も多...
教育(高校生)
2022.09.29
-
P検の勉強法とは?難易度や合格率・おすすめのテキストもあわせて紹介 「P検を取ると大学入試で優遇されるって聞いたけど何?」「高校生・中学生だったら何級をとればいいの?」「P検って学校で受験できるの?もし学校の受験日に受験が無理な時はどうしたらいいの?」このように、P検という言葉を聞いたこ...
教育(高校生)
2022.09.29
