指しゃぶりをやめさせる方法|する理由や気になることもあわせて紹介
育児
2022.01.04
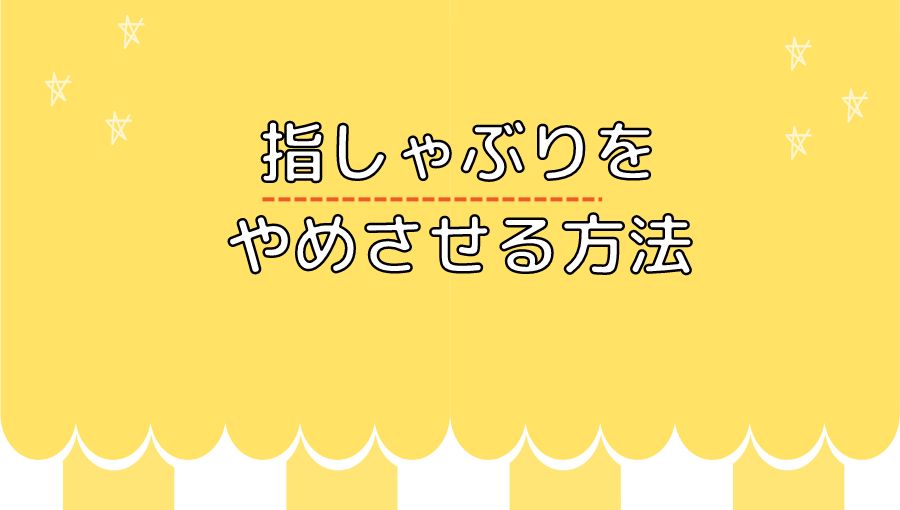
目次
「うちの子、いつまでも指しゃぶりしているけどやめさせなくてもいいの?」
「指しゃぶりは歯並びに影響すると聞いて、心配」
「指しゃぶりをやめさせるのにいい方法はない?」
このように、赤ちゃんの頃にはかわいいと思えていた指しゃぶりでも、子どもが大きくなってくると「やめさせたい」と考える保護者は多いのではないでしょうか。例えば、テレビや雑誌で、指しゃぶりが歯並びに悪影響を与えると聞けば、不安になることもあるでしょう。
この記事では、子どもが指しゃぶりをする理由や気になること、指しゃぶりをやめさせる方法などを詳しく解説しています。また、指しゃぶりをやめさせるためのおすすめアイテムも5つ紹介しているため、指しゃぶりを卒業するヒントが見つかるでしょう。
子どもの指しゃぶりに悩んでいる方は、ぜひこの記事を読んで参考にしてください。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
指しゃぶりをする理由4つ

指しゃぶりは赤ちゃんの頃から見られます。吸う指は親指だったり、中指と薬指の二本指だったりとさまざまです。
赤ちゃんの手遊びの1つとして始まる指しゃぶりですが、成長してもやめられなければ心配の種になります。しかし、まだ言葉を上手に話せない小さな子どもに確認することは難しいでしょう。
ここでは、指しゃぶりをする理由として挙げられるものを4つ紹介します。
1:癖になっているだけ
生まれてから数ヶ月した赤ちゃんは、手遊びをしたり、なんでも口に入れたりしてさまざまな感覚を学んでいきます。
1度指を口に入れたことで、そこから指しゃぶりが始まることも多いと言われています。
大きくなると徐々に指しゃぶりは少なくなっていきますが、癖になってしまってやめられないという場合もあるでしょう。
2:もっと遊んでいたかった
赤ちゃんにとって、指しゃぶりは遊びと学びの手段であると言われています。赤ちゃんは、自分の指を口の中に入れることで指を強く吸ったり、口の中を確認したりしています。
その遊びの延長で、指しゃぶりを続けている可能性もあるでしょう。
3:することで安心している
指しゃぶりは、お母さんのおっぱいを吸うように強く吸うこともあれば、ただ口に入れてしゃぶっているだけのこともあります。
どちらの場合でも、赤ちゃん自身がおっぱいを吸っているかのような状態になることで、安心を得ていると言われています。
赤ちゃんが不安そうであれば、抱っこなどをしてあげるといいでしょう。
4:精神的な負担や不満を感じている
指しゃぶりをする理由として、例えば幼稚園に入園して環境になじめなかったり、兄弟が産まれ家族構成が変わったり、子どもが何らかの精神的負担や不満を感じていることも挙げられます。
赤ちゃんや小さい子どもの指しゃぶりは、遊びや安心感を得るためだと言われています。また、少し大きくなってきた子どもが指しゃぶりをする場合は、気持ちを落ち着かせるためにすることが多いでしょう。
このような場合に無理やり指しゃぶりをやめさせるのは、子どもの精神面にとって逆効果になる可能性があります。
幼稚園に通う年齢の子どもが指しゃぶりをしていたら、子どもの精神面を注意深く観察してみましょう。
指しゃぶりで確認したいこと3つ

いつまでも子どもが指しゃぶりをやめないと、不安になることもあるでしょう。そのような場合は、1人で悩まずに、子どもの健診で医師や相談員に話してみでも良いでしょう。
ここでは、子どもがいつから指しゃぶりをして、いつまで続けるのかなどをチェックしてみましょう。
関連記事一覧
-
叱ると怒るの違い ポイント5つ 親が子供を叱ると怒るの違いは重要な親子コミュニケーションの一部で、以下のようにいくつかの主要なポイントで区別することができます。目的叱ることは主に教育的な目的があります。子供の間違った行動を正し、正しい行動を学ばせること...
育児
2023.07.31
-
今が旬!「きのこ」を味わおう 準備も簡単!きのこの食育きのこは手で簡単にほぐすことができるので、1歳のお子さんから「食材に触る」体験ができます。一般的なきのこは通年手に入るものなので、単独で使っても秋らしさを感じることは難しいかもしれませんが、いろい...
育児
2022.10.13
-
懐かしの給食の味をご家庭で!「きな粉揚げパン」 揚げパンの始まり揚げパンは昭和27年、東京の大田区の小学校で生まれました。風邪で学校を休んだ生徒に栄養をつけてもらおうと、残ったパンで作ったことがきっかけといわれています。現在では衛生的な側面から休んだ生徒に給食を届ける...
育児
2022.10.13
-
会話が苦手だと感じている人の特徴は?克服方法やポイントについても紹介 「会話への苦手意識はどうすれば治る?」「話し上手になるには何をすればいいの?」このように、会話に苦手意識を感じている方は沢山の疑問や不安があるのではないでしょうか。 この記事では、会話が苦手な人の傾向、会話が苦...
育児
2022.09.29
-
子供への愛情表現が苦手のままだとどうなる?愛情不足が及ぼす影響や克服法を解説 「子供への愛情が不足していると将来どうなる?」「愛情表現が苦手で子供に愛情が伝わっているか不安」「苦手な愛情表現を克服する方法が知りたい」子供の愛情不足が将来にどのような影響を及ぼすのか知りたいひともいるのではないでしょ...
育児
2022.09.29
